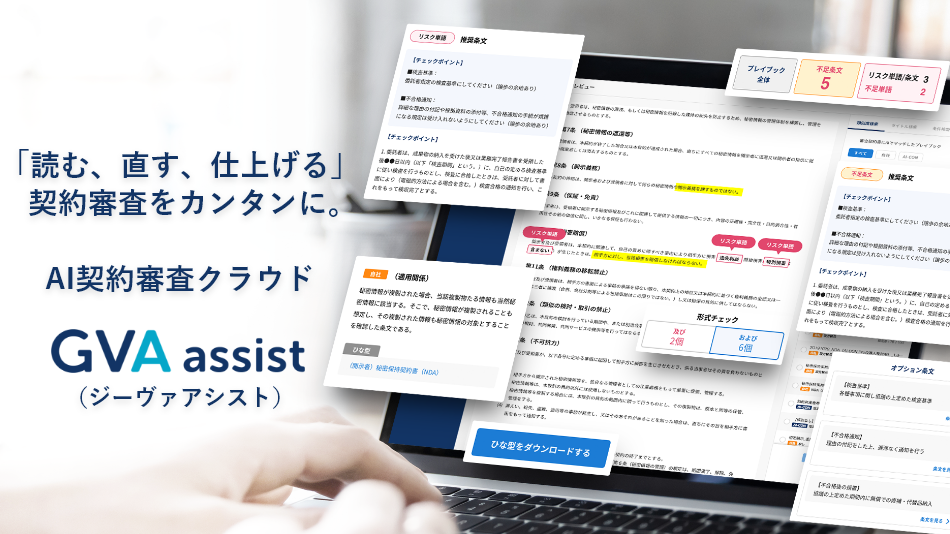2021年6月17日、日本エア・リキード合同会社で常務執行役員法務本部長、北東アジアCLO(日本・韓国)を務める乾山啓明様を講師にお迎えし、最新の法務事情、海外における企業法務の最新動向をお話しいただきました。
これから訪れる、法務パーソン激動の時代に必要な考え方とは? 激しい競争下で生き残っていくために必要なスキル、能力とは?
当日のセミナーの模様を、前後編に分けてレポートします。

乾山 啓明氏
日本エア・リキード合同会社
常務執行役員法務本部長、北東アジアCLO(日本・韓国)
総合商社の法務部で約20年間の経験(米国現法の法務責任者を経て、国内外の電力事業等を所管する法務セクションのヘッド)。 2018年に日本エア・リキード入社、同社GCを経て、2020年より現職。
過去の主要な法務担当案件として、インフラプロジェクトへの出資・JV・売却(LNGプラント、火力・太陽光・風力等の発電事業、水素関連事業等)、米国陪審訴訟を含む訴訟・国際仲裁など。
ニューヨーク州弁護士。
「これからの企業法務の話をしよう」
リーガルテックの導入などを通じて法務業務の効率化を実現した"その先"に、法務部門として何をすべきか、未来に向けて先進的な取り組みを実践されている法務の方とディスカッションするセミナーです。ゲストと弊社の山本との"未来の企業法務のあり方"に関する議論を通じて、法務部門の組織づくりのヒントをお届けします。
目次
競争相手は「隣の人」から「海外の法務パーソン」に
乾山:
前編では、外部の法律事務所と企業で働く法務パーソンとの競争関係が始まるよという話をしました。
もうひとつの競争はすでに始まっているのですが、それは「法務内での競争」です。この法務内での競争には、さまざまな意味が含まれています。
典型的なのは、ある一定の企業規模になると、法務の拠点を日本だけではなくて海外に置くようになるという動きです。実際に事業を行っている国、中国であれば中国、アメリカならアメリカと、世界各国に法務部門の拠点を置くようになっています。
従来の日本企業では、海外に拠点を展開しても、法務のジャッジは日本で行うのが一般的でした。本社は日本にあり、経営陣も日本にいることから、意思決定も日本で行うのが自然だったからです。
その後、海外の現地法人にリーガルチームを設け、そこで発生する法務業務や課題は、その国の弁護士により解決する企業が増えてきました。近年ではさらに状況は進み、各国のリーガル拠点を有機的に結び、グローバルなワンチームで課題に当たる日本企業が現れています。
そうなると、本社は日本にあったとしても、リーガルの拠点は全世界にある。ならば、日本の法務チームが担当をしなくても、案件の性質に応じてもっともふさわしいリーガル担当者が、地域を問わず担当すればいいのではないか、という議論が出てくるわけです。
さらに、日本企業が海外進出をしていくとなると、契約書において準拠法が日本法ではないケースが珍しくありません。案件によっては契約関連文書で日本語を使わないケースも増えていきます。そういう案件では、日本の法務チームが必ず担当しなければならないという理由はありません。
これまで日本企業の法務部門では、トップに法務部長がいて、その下に法務のセクションや担当者が置かれるというヒエラルキーがあり、それとは別に海外は海外で法務組織があるという組織構造だったと思います。また、企業によっては、既にグローバル・ジェネラルカウンセルを設置しているところもあるかと思います。
しかし、今後10年で加速する可能性がある試みは、従来のような特定の国の法務部長をトップにしたピラミッド型の構造ではなく、国を意識せずに働く動きだと思っています。国ではなく、プロジェクトごと、あるいは取り扱い分野ごと、あるいは一定の地域ごとに担当するという動きです。
この動きが進むとなにが起こるのか。世界各国の法務パーソンが「ライバル」になります。
これまでは日本には日本語の壁、あるいは日本法の壁があったことで、日本の法務パーソンにおけるライバルは、「自分の隣にいる人」でした。「将来、私は法務部長になるんだ」と、隣の席の人と競争をしていたかもしれませんが、今後の競争相手はアメリカの弁護士かもしれないし、中国の法務パーソンかもしれません。
いままで日本語の壁、あるいは日本法の壁、あるいは日本文化の壁、さまざまな要素に日本の法務パーソンは守られてきました。しかし、これらの壁がなくなることでそうは言っていられない状況になっていきます。
なぜ壁がなくなるのか。
ひとつは契約については世界における平準化・標準化が進んでいることが挙げられます。たとえば秘密保持契約です。日本でもそのような動きはありますが、世界でも共通のフォーマットを作ろうという動きがあります。なるべく契約書の中に考えうる条項を入れて、準拠法には頼らないようにしましょうという動きです。これが進むと、準拠法の意味が薄まっていきます。
これは秘密保持契約だけではなく、商取引、主に国際的な売買契約にもその傾向があります。すべての条項を契約書の中に入れましょう、もちろん契約書は重厚長大になっていきますが、この流れは止められないと思います。そうなると、究極的には日本法の知識も日本語の能力も必要がなくなります。必ずしも日本の法務パーソンが担当する必要はないといった考えが広がっていくことによって、法務内の競争は世界へと広がっていくわけです。
もうひとつ関連して、最近では日本国内の大企業であっても、日本人以外の方が日本の法務部長、あるいはジェネラル・カウンセル、CLOに就くことが増えてきたと感じています。
たしかにこれまでも、日本で事業を展開している外資系企業で、本国から来た人が法務部門のヘッドを務めるケースはありましたが、そもそも、外国の方がいわゆる日本企業の法務部で働くケースはそれほど多くはありませんでした。
しかし、2020年に行われた経営法友会による調査結果を見ると、日本の法務部で働く外国の方が増えています。サンプル数や対象企業の偏りはあると思いますが、経済法友会の調査に回答したおよそ1,200社で働く法務パーソンが約9,000人超いるなかで、外国籍弁護士は200人以上います。割合でいえば1〜2%かもしれませんが、確実に増加しています。
担当者レベルではなく、法務部門のヘッドに就く外国人の方も増えています。たとえば現在、ある大手の電機メーカーや大手のエネルギー会社、日本で最大規模の買収を行っている会社の法務部門のヘッドは外国の方です。
法務部門のヘッドには細かな日本法の知識は必要ありません。細かな点は日本法の弁護士、法律事務所に聞けばいいのであって、ヘッドに求められるのは法務全体のデザインや、どうやればビジネスをうまく進められるのかといった考え方、法務部門のマネジメント力などです。これらの能力を求めるのであれば、日本人の法務パーソンである必要はありません。
今後10年でこの傾向はどんどん進むのではないかと思います。
法務部門のヘッドが外国人になると、日本にいるメンバーだけで仕事をするのではなく、世界各国の法務パーソンを活用すればいいじゃないか、またはワン・グローバル・チームで特定の案件についてチームを募ればいいんじゃないかという考え方にシフトしていくことが予想されます。そこで、必然的に世界的な法務パーソン同士の競争が始まるわけです。
これが2つ目の競争の話でした。
専門知識から言語まで 法務パーソンに求められる「スキル」
山本:
ありがとうございます。非常に興味深い話だなと思いました。
自分の得意とする準拠法以外に立脚してマネジメントし、ヘッドになるというのは成り立つのかなと思っていたのですが、経営と法務をブリッジするような役割を果たし、組織全体のマネジメントができれば、そういう人がヘッドになったほうがいいのかなと思いました。
さまざまな国をまたいだ法務のメンバーの中で出世していくというところで、先ほど重要な能力をいくつか具体的にお話しいただきましたが、この辺を深堀りして聞かせていただければ、今後の企業法務で身に付けなければならない重要な能力がわかるのではと思いました。
乾山:
ポジションとして法務のヘッド、経営層に近いところは、必ずしもその国の文化や準拠法の細かな知識がなくても務まると思いますので、それらのポジションについては競争関係がいま以上に激しくなると思います。
一方で、実務に近いところでどこまで競争が激しくなるかというと、これはまだまだ時間がかかると思います。先ほど少し触れましたとおり、準拠法が果たす役割はどんどん少なくなっているとは言えると思います。
証券法や独占禁止法、特にカルテルの分野では各国の公正取引委員会がお互いに情報交換しながらやり取りする時代になっていますし、個人情報保護の関連でも、最近、日本とEUで個人データに関する保護レベルについて相互の十分性を認証しました。
そういう意味で法律自体のコンバージェンス(収斂)も起きている状況にあります。
紛争解決の分野においても、既に国際仲裁についてはニューヨーク条約があって、仲裁判断については(一部留保はありますが)加盟国の仲裁判断であれば他の加盟国のどこの国でも執行できるようになっていますが、昨年にはシンガポール調停条約が発効しました。
国内ビジネスに特化した企業ではあまり変化は感じないと思いますが、自社内に少しでも海外向けのビジネスがある場合、環境はどんどん変わっていくと思います。
では、そのような状況下で、どのようなスキルや経験を身に着けなければならないのか。特効薬はないと思っています。
参考になるのは経産省が出している「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能のあり方」という提言文書です。報告書の中で今後、我々に必要なスキルとマインドセットが挙げられています。我々が磨かなければならないものとして、自社の商品知識、ビジネスへの理解、これが大前提です。もちろんビジネス環境、文化への理解、あとはリスクの発見能力ですね。
私は発見能力に加えて、分析してどこまでリスクを取れるのかを判断するリスク感度が必要だと思っています。これは経験によって養われるものなので、初めは怖いのですが、ここまでのリスクは取れるという勘が出てくると、リスクテイクに関するアドバイスもできるようになっていくと思います。
次にコミュニケーション能力。言語能力もまだまだ重要です。世界でビジネスをする場合、英語は最低限のコミュニケーション・ツールです。これがないと海外との競争、海外の法務担当者としての競争にも負けてしまうと思います。
会計、財務、ITの知識も必要です。そのなかでも重要なのはITだと思っています。昔は法律事務所でも、弁護士が(契約書に)手書き修正したものを、秘書がタイプし直して書類を作っていました。しかしいまは、Wordなどを使って全部弁護士本人が修正しているケースが多いと思います。
これは法務パーソンでも同じです。自分で効率的に働く、そのなかで使えるITはどんどん利用することがますます求められていくでしょう。これはWordのスキルだけではなくて、いろいろな会社で契約レビューのソフトウェアなどを出していますが、こういったリーガルテックをどう使えるか。そういった能力も必要になっていくと思います。
山本:
ありがとうございます。これは興味本位でお伺いするのですが、乾山さんが社会人1〜5年目に、意識してご自身でスキルを高めるためにやっていたことで良かったなと思うことはなんですか?
乾山:
社会人1年目から5年目くらいですと、会社の中のいろいろな人と会おうという努力をしていました。ビジネスを理解するためというのはもちろんなのですが、なにか仕事をする際には誰かを巻き込まないといけません。これは誰に聞けばいいんだろうとか、そういったことがわからないままでは、仮に自分に能力があったとしても発揮できません。
誰がキーパーソンなのか、誰がどんな仕事をしているのか、それを知るためにたくさんの人とランチをすることを心がけていました。いまはコロナ禍でそういった動きは難しいかもしれませんが、たとえばチャットする、コーヒーブレイクをオンラインで行うことなどはできるのではないかと思います。
質疑応答
山本:
ありがとうございます。参加者の方々からの質問です。
質問:契約業務と一般法務業務(第1ディフェンスライン)、コンプライアンス、リスク管理(第2ディフェンスライン)が法務業務に含まれていると思いますが、今後、法務部門としてどちらに注力したほうが良いでしょうか。
乾山:
非常に答えるのが難しい質問ですね。これは、個々の企業のビジネスや方向性によって変わると思います。
企業が特定の業法に服しているような業種だと、コンプライアンス。一般的な贈収賄や競争法だけのコンプライアンスだけではなくて、金融コンプライアンス、あるいはその他、安全保障貿易管理など、幅広い分野があると思います。企業によっては否が応にもそちらに注力せざるを得ず、法務だけではなくて専任の別部署もある企業も多いのではないかと思います。
一方、企業によっては国内中心だったものが国際的なビジネスが増えてきたので、契約書、英文契約書を整備しなければならない、そちらに時間を割かないとならないといった企業もあると思います。
一概には言えないものの、私は今後、いわゆる契約業務は濃淡をつけて見ないといけなくなるのではと感じています。たとえば秘密保持契約は向こう5年ほどで、日本と世界とで標準の雛形がかなり整備されていくと思います。秘密保持契約はほぼ企業法務内で見る必要がないところまでいくのではないでしょうか。
加えてリーガルテックの進化によって、秘密保持契約や単純な業務委託契約は、ある程度オートメーション……とまでは言いませんが、かなり時間を節約できる分野になっていくと思います。
その一方で、コンプラインスやリスク管理ですよね。出てきたリスクをどうマネージしてどう対処するかというほうは、一層重要性を増していくでしょう。法務の中にいる人間の力の入れ方としては、やはり相対的に見るとコンプライアンス、リスク管理に重点が置かれるのではないかと思っています。
山本:
まだいろいろ聞かせてほしかったのですが、あっという間に時間が来てしまいました。今日は貴重なお話をありがとうございました。
乾山:
企業法務の歴史はまだまだ発展途上にあると思っています。こういった機会をいただいたことですし、微力ながら私も国内の企業法務の底上げを頑張りたいと思います。
本日はありがとうございました。