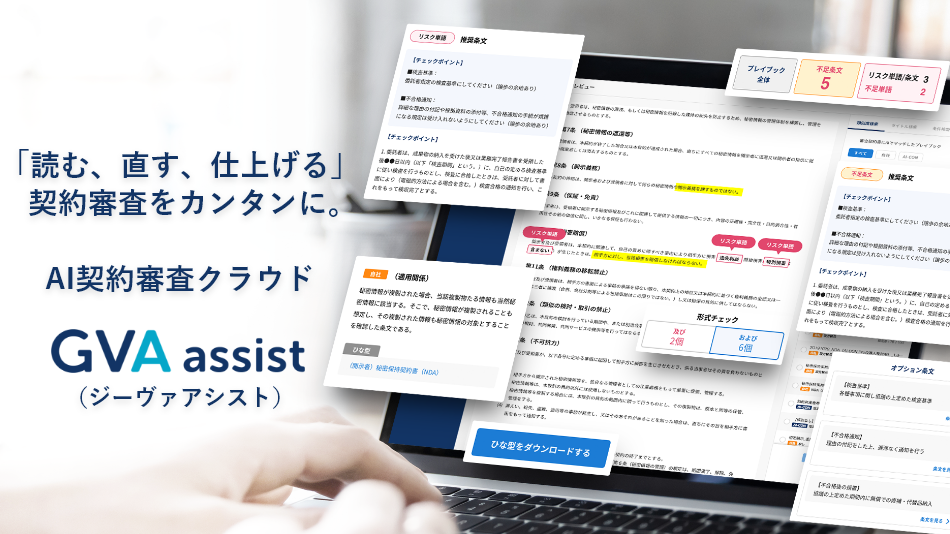GVA TECHでは、テクノロジーで契約業務に関する課題解決を目指すだけでなく、企業の法務パーソンの方々のお役に立てる情報発信を行っています。その一貫として、企業法務に携わる方々向けのセミナーも随時開催しています。
本セミナーでは、海外M&Aの実務経験が豊富な日比谷中田法律事務所 井上 俊介弁護士に、思わぬ落とし穴とその回避方法について解説いただきます。
本まとめは前後編でセミナーをレポートいたします。

井上 俊介 先生
日比谷中田法律事務所
パートナー弁護士
海外M&Aと競争法対応の専門家として、100件超のM&A案件に関与。全世界の法律事務所との緊密なネットワークを生かし、日系企業の海外M&A・競争法対応を一気通貫でサポートすることを得意とする。M&A・競争法に関する論考・セミナー多数。M&A・競争法の2分野でBest Lawyers in Japan に3年連続選出中。東京大学法科大学院、英ロンドンスクールオブエコノミクス卒。長島・大野・常松法律事務所、Freshfields Bruckhaus Deringerを経て現職。東京大学法科大学院未修者指導講師。
目次
海外競争法届出とガン・ジャンピング
次のテーマは海外競争法届出とガン・ジャンピングです。これも海外M&Aでは必ずと行っていいほど問題となる重要なテーマです。
2016年7月、テンセントは中国で音楽ストリーミング事業を行っていたCMCという会社の61.64%の株式を取得し、同社とデジタル音楽事業の新会社を設立することを公表しました。
テンセントのマーティン・ラウ総裁は「新会社はテンセントのデジタル音楽・関連事業の基幹企業となるだろう」と、このM&Aの価値を語っていました。こうして設立されたテンセント・ミュージックは2018年12月にアメリカで上場を果たし、上場日には時価総額230億ドル、約2兆6000億円に達しました。
ところが、この取引の公表から5年経った2021年になって、中国の競争当局はこのときのCMC株式取得に関して、テンセントに対して50万中国元、日本円で約853万円の罰金を科しました。
これは大した金額ではないように見えますが、法令で定められた最高額です。
その理由として挙げられたのが、テンセントが2016年にCMC株式を取得した際に、必要な競争法届出を行わなかったことでした。さらに、テンセントに対しては市場における競争を回復させるための問題解消措置を講じることを命じました。
欧米ではGAFAのような巨大IT企業に対する規制が強まっていますが、中国でもインターネット大手企業への取締りを厳しくする傾向にあり、本件はその一環ではないかという見方もあります。
実際に同じ時期に中国の配車アプリ大手のDiDiが日本企業と設立した合弁会社において、必要な競争法の届出がなかったとして、日本企業も罰金の対象となっています。
競争法届出の落とし穴
先ほどの事例は中国のものでしたが、競争法届出制度は世界100カ国以上で採用されています。
そもそも競争法届出とは何でしょうか。
競争法届出とは、一定の要件を満たすM&Aを行う際に(多くの場合取引実行前ですが)、取引について競争当局に届け出てその承認を得ることを義務付けている制度です。これにより、市場における競争に悪影響を及ぼすM&Aを事前に禁止するのがその目的です。
この届出を怠ることをガン・ジャンピングといいます。
近年、どの国でもガン・ジャンピングに対する執行が強化されていて、罰金も高額化しています。外国企業が摘発を請けるケースも増えています。アメリカ、EU、中国あたりは気をつけているという企業も多いのですが、最近は特に新興国でもガン・ジャンピングに対する執行を強化しているため注意する必要があります。
競争法届出で意外と理解されていないのが、競争に対する悪影響がないM&Aであっても届出は必要ということです。ときどき、「当社も買収対象の会社も市場シェアは非常に小さいので届出はいらないですよね」と聞かれることがあるのですが、そういうことではありません。売上基準、資産基準などの届出要件にヒットすれば届出義務が自動的に生じます。
ある取引について競争への悪影響があるかないかというのは、届出を受けて当局が審査することです。要件を満たすにも関わらず、この取引は市場への影響はないと勝手に判断して届出を怠れば、届出義務違反になります。
この競争法届出で特に注意したいのが合弁会社、ジョイントベンチャー(JV)の設立です。
届出が必要かどうかは買主グループと買収対象企業の売上高を基準に判断することが多いのですが、合弁会社の設立の場合は合弁パートナー全部の売上高で判断することになります。その結果、合弁パートナーが大企業同士だと合弁会社自体の売上が小さくても、多くの国で届出が必要になることがあります。
日本企業同士が日本でJVを設立する案件で、日本以外の5〜6カ国で届出が必要になるといったケースも珍しくありません。
また、海外では外資規制等の関係で、現地パートナーと合弁を設立するケースもよくありますが、そういった取引では現地の合弁パートナーが競争法届出についてよく分かっていないということも多いので、相手方の担当者に競争法届出が必要であることを説明して協力してもらう必要があります。
競争法の落とし穴の回避方法
競争法届出の落とし穴にはまらないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
回避策:定石)競争法届出要否分析
まず定石として考えられるのが、M&A取引の実施前に全世界の競争法届出の要否を分析することです。
競争法届出が必要になる要件は国によってまちまちなのですが、売上高を基準として用いる国が多いです。各当事者の国別の売上高を入手して、それを利用して一つ一つの国ごとに届出要件を満たすかどうかをチェックする方法があります。この方法は、確実性は高いのですが時間と費用がそれなりにかかります。また、会社によってはすべての国について国別の売上高を出すのが難しい場合もあります。
このような大々的な調査を行うのが難しい場合、次善の策としては簡易的な調査で済ませることもよくあります。たとえば自社と買収対象企業がどちらも売上高を有する国とか、自社にとって特に重要な国についてのみ届出が必要かどうかの調査を行う方法です。
この方法はもちろん完璧ではないので、調査を行わなかった国で届出要件を満たすリスクは残るのですが、少なくとも一定のリスクは回避できます。
回避策:妙手)現地法律事務所から意見取得
こういった分析を行うと、思わぬ国で届出要件を満たすことがあります。これはこうした国々では売上基準が非常に低く設定されていたり、要件が不明確にしか定められていなかったりするのが原因です。よく出てくるのがベトナム、ウクライナ、インドネシア、ポーランドといった国々です。
そのような場合、すぐに届出の準備をしても良いのですが、現地の法律事務所に意見を求めて法令の解釈や実務の運用上届出が不要と整理できないかを確認するのも一考の価値があります。
こうした整理を行う際には、自社にとってのその国の事業上の重要性や将来、過去の取引との整合性といった事情も考慮要素となります。
こぼれ話
競争法はしばしば「純粋な競争保護ではなく政策目的で利用されているのではないか」と指摘されることがあります。2019年の新聞の見出しですが、「中国独禁当局 フォード合弁に罰金 米中摩擦が背景か」とあるのですが、これもそのような見方の一つと言っていいでしょう。2012年頃には日本企業が関与するM&A案件について中国での審査が非常に長引いたことがあって、そのときは尖閣問題で日中関係が悪化していたので、中国政府の嫌がらせだという噂が広まったことがありました。
この件について中国の弁護士に聞いてみたところ、当時は中国も届出制度を導入したばかりで人手不足と経験不足のために審査が遅れていた、というのが真相のようです。
また、つい先日ウクライナで競争法届出を担当したケースがあったのですが、ウクライナ当局からは当事者のロシアとの関わりについて質問を受けました。これは普通に考えれば市場における競争とは無関係ですので驚きました。結論として、国によっては政策目的で競争法届出を使用する可能性もあるのかもしれません。
海外法律事務所の選び方・使い方
最後は今までと趣向を変えて、海外法律事務所の選び方、使い方についてです。
日本企業による海外スタートアップへの出資
こちらは私がクライアントから聞いたり、実際に経験したりした事例を組み合わせた架空の事例です。
ある日本のメーカーがある国のスタートアップへ少額のマイノリティ出資(1億円以下)を検討していました。そこで、DDと契約交渉のために現地である程度名の知れた法律事務所を起用することにしました。
すると、その法律事務所は少額のマイノリティ出資にも関わらず膨大なDD質問リストを作成して非常に工数をかけてDDを実施しました。終わってみると、案件自体は確かに成功したのですが、弁護士費用だけで1000万円近く掛かってしまいました。
たしかに慎重にリスクを検討するに当たってDDは必須なのですが、案件の規模に照らして不相応な費用をかける必要はありません。
国内案件だと法律事務所も顧客が求めているレベルや予算感などを配慮してくれることが多いのですが、海外の法律事務所だとちゃんと前もって言っておかないと伝わらないことがあります。
海外法律事務所と付き合う上での難しさには一体どういうところにあるのでしょうか。
まず選択の難しさが挙げられます。
自社が新たに進出するに国だと、付き合いのある事務所がないケースがよくあります。そこで、知名度や規模で法律事務所を選ぶことがありますが、事務所の知名度や大きさは実際には仕事の質とは比例しないことがあります。
次に、法律事務所の質を評価する難しさが挙げられます。
まず、海外M&Aの経験が乏しいとコストの相場観がないため、相手の提示する費用が仕事内容に見合っているかどうかの判断ができません。
さらに、案件にとってなにが重要なポイントかをクライアント自体が把握できていないケースもあります。そうすると、法律事務所の仕事がそのポイントを捉えたものかどうかの判断も難しくなります。
最後に、統制(コントロール)の難しさがあります。
海外法律事務所をうまく使いこなすには、こちらのニーズをしっかり伝える必要があります。海外法律事務所に最高のパフォーマンスを発揮してもらおうと思えば、自社にとってのこのM&A案件の位置づけや目的、買収しようとしている対象会社はどういう会社で、どこに魅力を感じて、どういうところを心配しているのかをしっかり伝える必要があります。
それが時差や距離、言語、文化の壁もあってうまく伝わっていないケースを多々あります。また、意外とありがちなのが海外の弁護士のアドバイスを金科玉条のようにありがたかってしまうケースです。
たとえば、現地の事務所に大規模な贈収賄DDやFTO調査を提案されると必要性を吟味することなく、時間とお金をかけてこれらの調査を実施することがあります。
逆に、海外事務所に対して不必要に居丈高に振る舞うケースも見たことがあります。海外事務所にちょっとしたミスがあったり時間に遅れただけで叱り飛ばしたり執拗に責めたりすると、これも海外事務所のベストなパフォーマンスを引き出す妨げになります。
海外の法律事務所を上手に使いこなすコツ
では、海外事務所をうまく使いこなすにはどうすればいいのでしょうか。まず、定石から見ていきましょう。
回避策:定石)相見積もり
ひとつ目は複数の事務所から見積もりを取って内容を比較することです。これは当たり前にやっているという会社が多いと思います。
回避策:定石)スコープを限定したメリハリの利いたDD
ふたつ目として、DDを行う場合にそのスコープを限定して、メリハリの利いたDDを行うことも重要です。
回避策:定石)キャップによる予算管理
3つ目としてキャップをはめるという言い方をしますが、予算管理の方法として報酬の最大額を事前に決めてしまうやり方もあります。
これらはいずれも海外事務所のコスト管理の手法です。次により進んだ方法も見ていきます。
回避策:妙手)各国ごとに選択肢を持つ
どういうことかというと、国ごとに複数繋がりのある法律事務所を作っておいて、どの事務所のどの弁護士がどの分野に強くてどれくらいの費用感なのかをきちんと押さえるということです。
これにより、案件の規模や特性に合わせて法律事務所を使い分けることができるようになります。
回避策:妙手)日本法弁護士(ディール・カウンセル)による監督
日本法弁護士による監督という方法があります。これは外資系企業のM&Aなどでは一般的なのですが、自社が海外事務所に直接指示を出すのではなく、海外事務所への指示・監督をディール・カウンセルという弁護士に任せる方法です。
海外法律事務所の選択もディール・カウンセルから適切な事務所を推薦させて、その中から選ぶことができます。また、海外法律事務所への具体的な指示も自社の意図を汲み取ったディール・カウンセルに行わせます。これにより、効率的・効果的な案件の遂行を期待できます。
特に複数の国にまたがる案件では窓口を一本化できるので、自社がいろいろな国の法律事務所に別々に指示したり、深夜早朝に現地事務所と会議を行ったりする負担が大幅に軽減できます。
まとめ
本セミナーについてポイントをまとめます。
定石を押さえつつ、案件ごとに最適なソリューションを柔軟に選択する
海外M&Aでとにかく大事なことは、場面ごとに正攻法、定石を押さえつつ、案件ごとに最適なソリューションを柔軟に選択するということです。
やるべきことは、国内M&Aと大きく変わらない
それは国内M&Aでも同じことです。海外M&Aであってもやるべきことは国内M&Aと大きくは変わりません。ですので、適切な対処さえ行えば、海外M&Aだからといって不安になる必要はありませんので、ぜひ楽しんで挑戦していただきたいと思います。
参加者からの質問と講師からの回答
セミナー後、参加者から多くの質問が寄せられました。ここではその一部を抜粋してご紹介します。
Q:先生の実績としてヨーロッパの化学メーカーが日本企業の事業を買収というのに興味を持ちました。なぜヨーロッパの企業が日本企業の事業の買収に興味を示したのでしょうか。
A:ヨーロッパのメーカーは、自動車の製造にも使われる製品を作っている会社です。
自動車の製造は現在非常にグローバル化していて、各自動車メーカーが世界中に工場を持って、世界中で色々なモデルを作っています。それに対してサプライヤーも自動車メーカーの作る場所ごとにグローバル供給をしているわけです。
グローバル市場になっているので、ヨーロッパのメーカーが日本の企業を買う、日本の企業が海外の企業を売買するというのは頻繁に行われています。その一環で、ヨーロッパのメーカーが、日本企業が行っていた事業に興味を持って買収したという案件です。
売り手の日本企業はその後別の会社を買収したようなので、選択と集中、要らなくなった事業を売却して必要な事業を買うという流れの中に位置づけられるディールだったのではと思っています。
Q:売主側が売却で贈収賄をもみ消すことはあるのでしょうか?意図的に巧みに違反逃れをするということですか?
A:売主側が違反していることを知りながらそれを隠して売り抜けたということになれば、それは表明保証違反などで売主側の責任を追及できるということもあると思います。むしろ、売却側も贈収賄について知らなかったというケースの方が多いのではないかと思います。
意図的に巧みに違反逃れをした場合であっても、買収をしたあとに調査をして自主申告をした結果、買った側は罰金を科されなくて売った側が罰金を課されたケースもあります。なかなか違反逃れをするというのは難しいケースが多いのではないかと思います。
Q:知的財産権が絡む場合は買収よりも第一ステップとしてライセンスを受けることを行うべきではないでしょうか?
A:そういうケースもよくあります。魅力的な特許を持っている会社がある場合に、ひとつは特許自体の譲渡を受ける、もうひとつはライセンスを受けてそれを使用する。みっつ目として、会社ごと買収する。3つくらいの方法がパッと思いつきますが、ほかにもいろいろな戦略があると思います。
最初はライセンスでもいいと考える会社もあるかもしれませんし、いきなり買収もありえます。良し悪しがそれぞれあるので、その中で戦略を決定していくことになります。
Q:贈収賄に関してリスクが予想される場合に、贈収賄にスコープを絞ってDDを行う発想を初めて認識しました。このような贈収賄DDを担当するのはどのような組織ですか?法律事務所、調査会社、コンサル会社などですか?また、具体的にどのようなことを調査すれば贈収賄リスクを把握できるのでしょうか。
A:法律事務所と会計事務所が共同して行うケースが多いかと思います。会計事務所の行う会計DDの中で怪しいお金の流れが出てくることがあります。それが法律に違反するかどうかは弁護士に判断になりますので共同で行うことが多いです。
私が過去に担当したケースでは、政府との関係がある会社のDDのなかで、接待費のような名目の支出が見つかり、これは調べたほうがいいなということで、サンプル調査をしました。
実際の支払を100件ほど拾ってきて、それぞれについて怪しいものではないかというのを検討する。その中で特にこれはどうなんだろうというものについて、より詳しく現地の法律事務所やFCPAに詳しい弁護士に意見を聞いて、最終的に結論を出すといったことをしたことがあります。
結論として法律事務所と会計事務所、コンサルファームもあるかしれませんがそういった調査を行っている会社と一緒にやるというのがオーソドックスな手法だと思います。
Q:先進国以外だと知的財産権の権利化に関する制度自体が不十分という国もあると思います。そのような国の企業が対象のM&Aの場合はどうすればいいですか?
A:知的財産について保護が十分ではない国は結構あります。新興国などですね。そういう国はそもそも権利が保護されているかどうかの判断が難しいこともありますし、あるいは第三者の権利を侵害しているケースもあると思います。その分、しっかりと知財については見ていくことになります。最悪知財が守られていないリスクも考えながらディールを進めていくことになります。
Q:それほどの高額と思えないような罰金ならば、届出義務違反を甘受すべきという風潮はありますか? 届出を行うデメリットについても教えてください。
A:まさにこれも非常に重要な論点になるかと思います。中国のケースでも50万中国元、1000万円以下ですので、これなら届出をしないでもいいやと考える会社もあるかもしれません。
ただ、競争当局もその点を懸念していて、ガン・ジャンピングに対する執行を強化し、罰金も高額化する傾向にあると言われています。中国でも、届出漏れに対する罰金額の上限を引き上げる改正を検討中と聞いています。
Q:競争法届出に関して。合弁パートナーの売上が合算になるということですが、設立済の会社に対して共同出資する形でも同じような考え方になりますか?
A:JVを設立する場合には2つあって、ひとつは二つの会社がそれぞれ何%かずつ出資して新しい会社を作るケース。グリーンフィールドJVといいますが、この場合は、多くの国ではJVパートナーの売上高が基準になります。
もう一つのやり方として、もともと一社が持っている100%子会社である場合に、別のパートナーが新たに出資する、あるいは100%持分のうちの半分くらいの譲渡を受けて新たにJVにするというケースもあります。
国ごとに細かいルールがあるので一概には言えないのですが、この場合も、競争法の考え方としてはJVを新たに作ったということになりますので、その時点で届出が必要になります。この場合、多くの国では、JVパートナーに加えて、JV自身の売上高も考慮することになります。ポイントは、最初から作る場合も途中から作る場合もいずれも競争法届出の対象になるかの検討が必要という点です。
Q:贈収賄のリスクを契約上で手当したとしても、それを実際売主に損害賠償請求をするのは難しいとのことですが、実際に難しい理由について教えてください。
A:いくつかあります。契約書の中で補償請求ができるとされていても、それに限度が定められていることが多いです。ひとつは金額よる上限。何億円以上は責任を負いませんと定められているケースです。
もうひとつは時間による制限。買収後、何年後に損害が発生しても責任を負いませんと定められているケースです。罰金を受けたときに補償請求の請求可能期間がすでに過ぎている可能性もあります。罰金について全額が補償請求できるとは限らないのが実際です。
ここまでが契約書の話で、契約書に書いてあったとしても契約書の権利を行使しようとしたら、裁判や仲裁で勝訴の判断を得なければなりません。裁判や仲裁を行うにはお金も時間もかかります。また、勝訴の判断を得たとしても、それまでに売主がお金を使い果たしていれば、取り返すのは困難です。そうすると、契約上定められているから取り返せるよね、という話ではなくなってきます。そういう難しさがあります。
Q:海外M&Aの場合、DDも含めてディールの期間は通常どれくらいかかりますか?また、外部機関にDDを依頼した場合、報告書は英語になるのでしょうか?日本語翻訳では別料金が取られるのでしょうか?
A:前者の期間については案件や規模によってまちまちなので一概にはいえないのですが、日本でやるよりは時間が掛かるケースが多いと思います。そもそも海外M&Aの規模が多いので時間を取ってやることが多いですし、契約交渉にもそれなりに時間がかかります。
ただ、場合によっては短期間で案件を実行しないといけないケースもあるので、たとえば3ヶ月とかそういう期間で一気にすすめるケースもあります。通常は交渉開始から半年以上かかることが多いと思います。1年以上かかることもあります。
報告書については基本的にはグローバルにクロスボーダーM&Aをやる際の言語は英語ですので、日本企業と中国企業、日本企業とインドネシア企業の取引でも、英語で交渉することが多いと思います。
DDの言語も特に希望がなければ報告書は英語で出てきます。日本語に翻訳する場合には自社で翻訳してもいいですし、ディール・カウンセルがいる場合は、ディール・カウンセルの方で現地の法律事務所が作ったDDレポートを重要な部分だけ要約することもあります。