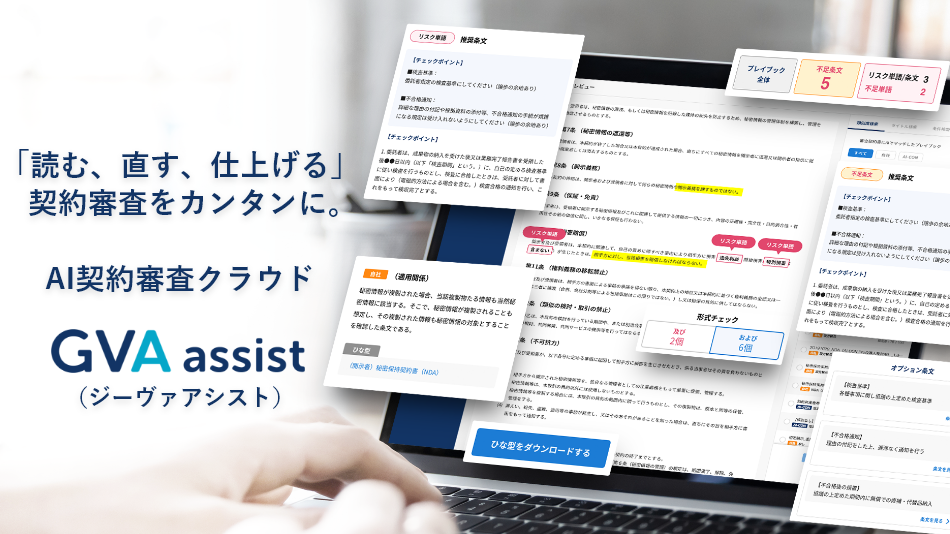2021年2月19日、総合エンタテインメント企業であるセガサミーホールディングス株式会社 法務知的財産本部 法務部 法務管理課 課長(当時)の東郷伸宏さんをお招きし、「これからの企業法務の話をしよう」と題したオンラインセミナーを開催しました。新たな価値を創造する法務人材になるために必要な考え方について、熱い議論が交わされました。当日の熱気あふれるセミナーの様子をお届けします。

ゲスト:東郷 伸宏 氏
セガサミーホールディングス株式会社
法務知的財産本部 法務知財ソリューション部
リーガルオペレーション課 課長
金融ベンチャー役員を経て、2006年サミー株式会社に入社。以降、総合エンタテインメント企業であるセガサミーグループの法務部門を歴任。上場持株会社、ゲームソフトウェアメーカー、パチンコ・パチスロメーカーのほか、2012年にはフェニックス・シーガイア・リゾート(宮崎県)に赴任。2017年現職。部門の立ち上げから、数十名規模の組織まで、多種多様な法務部門をマネジメントしている。
「これからの企業法務の話をしよう」
リーガルテックの導入などを通じて法務業務の効率化を実現した"その先"に、法務部門として何をすべきか、未来に向けて先進的な取り組みを実践されている法務の方とディスカッションするセミナーです。ゲストと弊社の山本との"未来の企業法務のあり方"に関する議論を通じて、法務部門の組織づくりのヒントをお届けします。
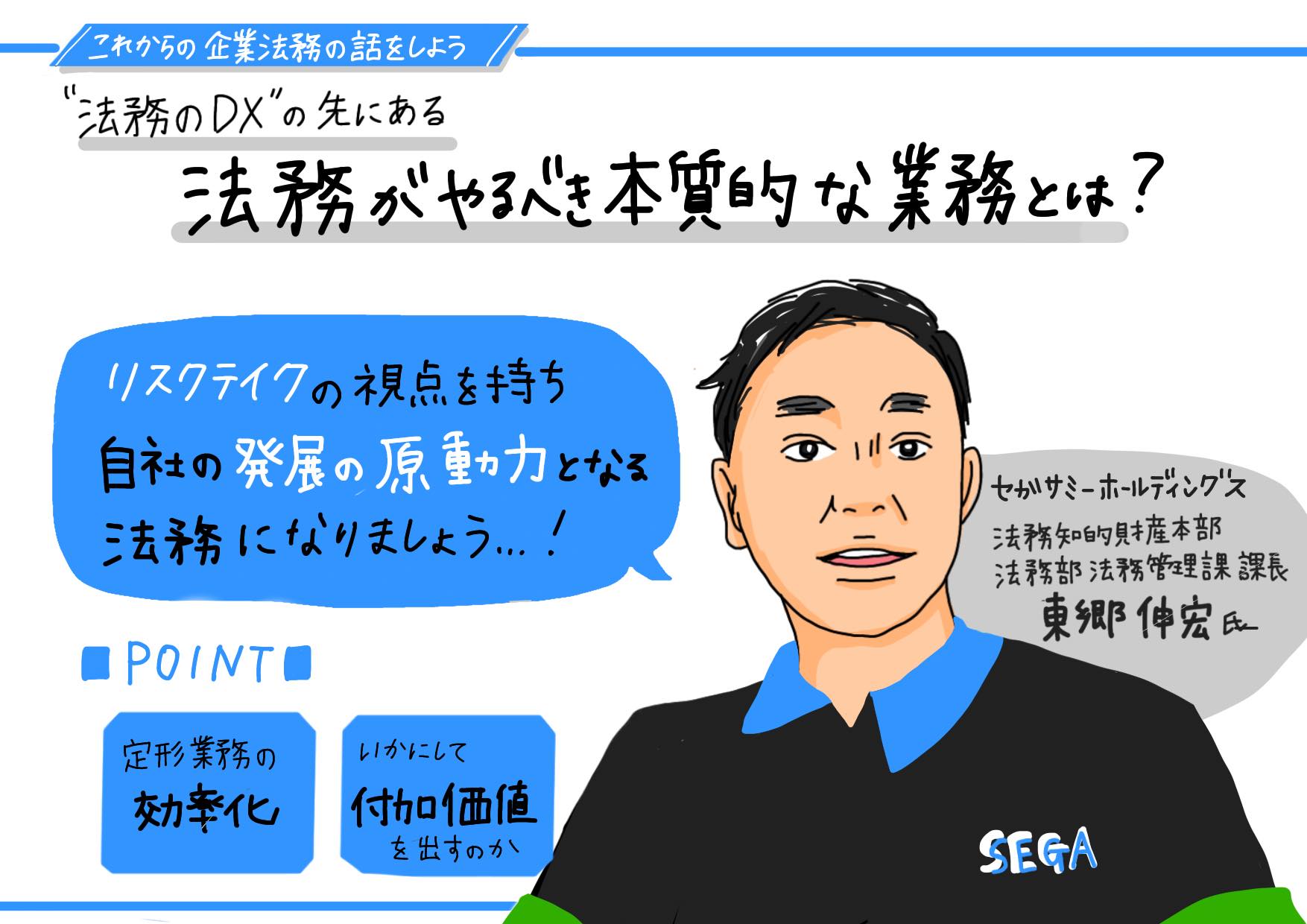
ディフェンシブになり過ぎない法務の「バランス」
山本 俊(以降、山本):
本日は、「これからの企業法務の話をしよう」と冠して、先進的な企業法務担当者さんに企業法務の「これから」をお話いただくセミナーの第2回目となります。
今回は、セガサミーホールディングス株式会社の東郷伸宏さんにお越しいただきました。
東郷 伸宏 さん(以降、東郷):
よろしくお願いいたします。
山本:
よろしくお願いいたします。お話を伺う前に、セガサミーさんの事業について教えていただけますか?
東郷:
大きく分けて3つの事業を展開しています。
1つ目は遊技機事業です。パチンコ、パチスロのメーカーという側面を持った企業です。当社は「サミー」を中心に、いくつかのブランドを持っているのですが、業界ではトップメーカーであることを自負してシェアを拡大しています。
2つ目は皆さんに特に馴染み深いのではないでしょうか。エンタテインメントコンテンツ事業です。セガのデジタルゲームやアミューズメント機器開発からおもちゃまで、多種多様なコンテンツを提供している事業で、アニメなどの映像制作も展開しています。子会社のトムス・エンタテインメントからは、「アンパンマン」や「名探偵コナン」、「ルパン三世」などを社会に提供しています。
3つ目はリゾート事業です。私のキャリアでも経験しているので思い入れの深い事業なのですが、日本における統合型リゾート(IR)への参入を目指して、現在は韓国でパラダイスシティというカジノを含むリゾートを運営していますし、ほかにも宮崎県にあるフェニックス・シーガイア・リゾートなども運営しています。そのほかにも、ゴルフ場の運営も手掛けています。
売上の規模は、コロナ前の数字としては連結で3,665億円です(2020年3月期)。
山本:
ありがとうございます。それではさっそく、いろいろとお話を聞かせていただきたいと思っているのですが、改めて、セガサミーさんの事業を見てみると、本当にやりがいがあるというか、法務が頑張れば頑張るほど事業の価値がどんどん上がっていく、そういうポテンシャルが秘められていますね。
東郷:
はい。新しいものにチャレンジして新しい価値を生み出していかないと、お客様に楽しんでいただけないし、ビジネスとしても成立しないと感じています。新たな分野に取り組んでいく際には、法規制や業界ならではのルールが立ちはだかる場面に多く出くわします。いかにそういう状況を乗り越えていくのかが、我々法務の人間に期待されているところです。
普段は、ゲームやパチンコ・パチスロといった既存のビジネスでも、規制と付き合いながら展開していますし、今後控えている日本の統合型リゾートについても、徐々に新しい法律が作られ整備されつつある状況ですので、法務としてその状況にアジャストして、新しい価値を生み出していくかを常日頃から考えています。
山本:
現状、法務部が抱えている定型的な業務と付加価値業務の割合について、東郷さんが考える理想的な配分はどれくらいですか?
東郷:
現在は契約審査が全体の業務の50〜70%を占めている状況です。ここから、DXを推し進めたりさまざまなルールの見直しを図ることで、定型業務の割合を約半分まで効率化し、新たに30〜40%の業務リソースを獲得できるのではないかと感じています。
そして、新たに獲得したリソースを、どのように新しい業務にシフトするかが今後の課題ですね。
法務は契約書を「見すぎてしまう」
山本:
セミナー冒頭で実施したアンケートの結果を見てみると、今日ご参加いただいている方々は、契約業務が業務量全体の約50%〜80%を占めているそうです。
皆さんこの業務量を圧縮したいと感じていながら、なかなか進まない、その原因について東郷さんはどのようにお考えですか?
東郷:
我々も効率化には常に取り組んでいて、例えば定形書式的な契約は審査を経ることなく締結まで進める仕組みを導入・推進しました。その過程で感じたこととしては、法務の皆さんは「契約書を見すぎてしまう、審査をしすぎてしまう」んですね。
要因はさまざまだと思うのですが、法務・企業法務の成り立ちから振り返ると、社内で締結される契約の審査業務が、まず誕生時のニーズとしてありました。そこから法務部門がスタートしたがゆえに、何から何まで審査することがルールとして最初にできあがり、そのまま硬直化して今日に至っていると感じています。
これは各社の状況や、法務部門の誕生からどれくらい年月が経っているかによって変わってくると思うのですが、時間を経ていくことで、契約がはらむリスクの度合いも下がっていくことが多いので、実際はそこまで丁寧に見なくても十分合意できる程度のリスクにとどまっている契約が、じつはかなりあるのではと思っています。
つまり、これまで敷いていたルールをいかに見直していくかが、今後の契約審査業務の効率化にとって重要なポイントになるのではと感じています。
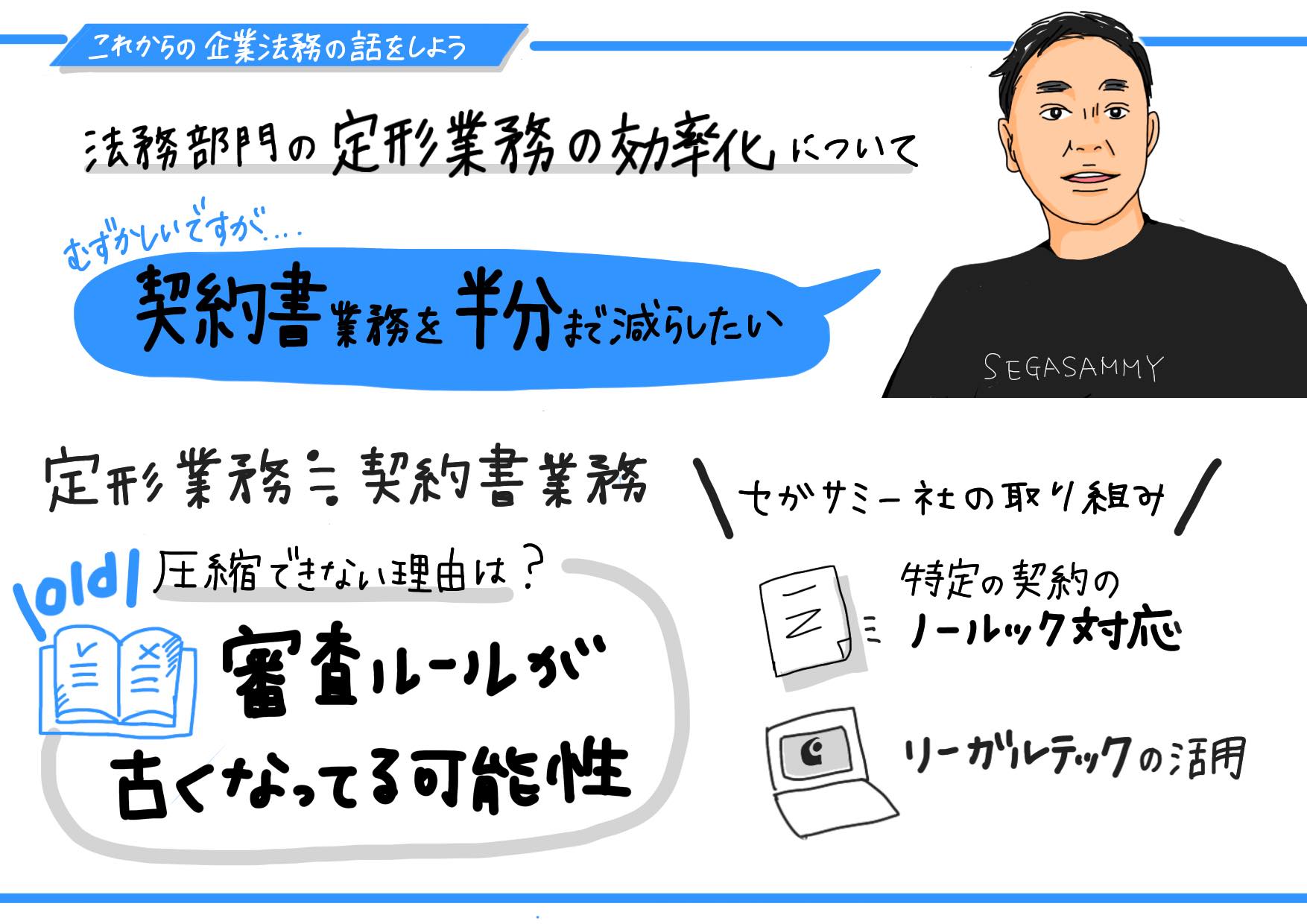
リスク分析・リスクヘッジとリスクテイクのバランス
山本:
契約書業務にしても、リサーチにしてもそうなのですが、法務リスクの分析というところが、法務部にまず初めに求められると思うんですね。次に、理論上はそのリスクを取るのか取らないのかといった判断も、法務はやっていると思うんです。ここのバランスについてどのようにお感じですか?
東郷:
これは永遠のテーマですよね。リスク分析を最初にやるということはみんなわかっているのですが、やりきれていないところがあります。やりきれていないとは、雑になっている、手が回らないということではなく、極端にディフェンシブになりすぎていたり、ゼロリスクを求めている、そんなところがあるように感じています。
法務が本来の意味でのリスク分析をしっかりと行うことで、「ここまではスルーしても会社にダメージはない」「ここまでは許容できる範囲」というようにリスクを洗い出せるようになれば、見すぎなくても良い部分、逆により丁寧に見なければならない部分が、精査されていくと思うんです。
ですが、やはり日々の契約書審査業務に押しつぶされてしまって、法務がそこまで踏み出せていないのが現状なのでは、と思っています。
山本:
本セミナーの第1回で、株式会社SHIFTの照山さんは、「経営陣・役員と、クオリティなのかスピードなのか、最優先となるポイントはどこにあるのかをグリップする」とお話されていました。御社ではいかがですか?
東郷:
我々はまだそこまではできていないのが現状です。会社としてどこまでのリスクを許容するのか、その線引きができていれば、その線に則って「ここまでは見よう」「ここから先は強引に行ってしまおう」という判断ができます。
その判断ができれば、法務部門の負荷は軽くできると思うのですが、多くの企業の法務部門責任者の方々は、契約審査業務の負荷を軽くしようという趣旨の話し合いを経営陣と持とうとすると、
「『楽をしようとしている』と捉えられるのではないか」
「『会社にダメージを与えようとしている』と思われるのではないか」
という、いわば恐怖観念に囚われてしまっているところがあるように見えます。
そのような誤解を防ぐためには、法務から経営陣に対して「空いた時間で新しく、このような付加価値を提供できます」といった約束をする必要がありますよね。
山本:
現状の制度や法務のポジションだと、どうしても減点方式になっているところがありますよね。契約書のトラブルがあったら全部法務のせいになってしまい、せっかくリスクを取ってスピードを早めたのに、何かあったときにはいろいろと言われてしまう。
東郷:
はい、現状の法務は残念ながらそういうことになりがちな部門なんです。
本来、ただしくリスク分析を行って、戦略的に判断して進んだ上で発生したトラブルであれば、それは想定内の出来事です。であれば、そのトラブルは許容範囲内であって、裁判に行っても問題なく対応できるわけですから、そこは許容していけばいいのではと思いますね。